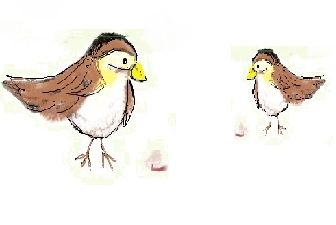「米倉社長、私はまだまだお役にたてる存在ではありません。メイクアップアーティストとして、できない事がたくさんあります。お金を貯めて美容学校に通うと決めたのですが、自分で生活するのはお金がかかります。今の職場はアパートの家賃も払ってくれているのです。」
「後、二年の猶予を下さい。それに、今は店を辞める訳にはいかないのです。最近、二人が辞めてしまって人手が足らない時に私まで辞めることはできません。二年の間に夜に近所の美容院で技術を身につけます。そして、美容学校の通信課程で資格をとります。」
佳代は電話で自分が思っている事を全て話すと、米倉社長は快く了承してくれた。
「期待してまっています。頑張ってください。」
現在の天王寺店は、二名欠けた人材がなかなか埋まらず新しく従業員が入ってくるまでの繋ぎで、他店から臨時で応援に来てもらっている状況だった。 佳代は、思いつくイベントや会社から提供されるイベントで全力で働いた。
化粧品店の仕事が六時に終わると、歩いて二分の同じビルの中の美容室で二時間毎日、タオルを洗ったり掃除をしたりと雑用をこなしながらの勉強だったが佳代は弱音を吐かなかった。カットはまだまだ先だが毛染めやカラーは店でも売っていたので理解するのは早かった。
シャンプーの仕方やブロウの仕方、カラーの巻き方等など教えてもらっている。雑用をして働く代わりに店が閉まる八時まで薄給だが、丁寧に教えてくれた。最近は、美容師の資格を取るため通信課程を受けている。
通信課程は三年間勉強するが、いずれは国家試験も受けるつもりだ。少しずつ米倉の事務所で働く準備が進んでいた。
オサムには、昨年暮れに会ったきりだった。福岡まで佳代が会いに行った。今回は間が空いている。最近は手紙ではなくお互いにアパートの電話で話していた。オサムが大阪出張も暫く無いと言うので六月ごろ、佳代は福岡へ行く予定にしている。
大阪は梅雨に入った。
一日中ジメジメと雨が降ったり止んだりと、気分的にうっとおしいが近くの公園の紫陽花がとてもきれいで忙しい佳代を癒してくれる。
佳代は、今日の福岡行をオサムに話していなかった。
いつも数カ月に一度、店の定休日である水曜日に出かけていたが今回、主任の気遣いで日曜日を有給として佳代に与えてくれたのだ。突然出向いてオサムを驚かせるのも楽しい。
新大阪から、朝九時発の博多行の新幹線に乗り昼過ぎに着いた。
空港線 各停 姪浜行 で天神に着いて軽く昼ご飯を食べて、市内のオサムのアパートをめざした。今まで何度も通った道なので迷う事はない。
日曜日なのでオサムは居るはず、連絡をしていないので少し不安はあったが出かけて留守であれば待っていようと簡単に考えていた。
レンガ造りのしゃれたアパートに到着した。六月の中旬、日曜日の午後半年ぶりの福岡だ。早く顔を見たい!と期待で胸がいっぱいの佳代だった。
佳代はオサムの部屋の前で深呼吸してからノックをした。オサムは驚いて喜んでくれるかな。ドキドキして出てくるまでの数分が長く感じた。
「はい。どちらさまですか?」
オサムの声は、くぐもった声だった。休みの日なので昼まで寝ていたのかな。
「佳代です。大阪から会いに来ちゃった。」
一瞬、間が空いてオサムの声が聞き取れない。
「びっくりするなぁ。突然だね。」「あっ、今、会社の同僚が来ているんだ。」
オサムは、ドアを開けたが佳代を中に入れるのをほんの一瞬だが、なんだか躊躇しているように見えた。一番辛かったのは、オサムには感じた事が無かった、佳代の頭の中のざわざわが湧き上がっている。佳代は、不安だったのだ。
「あっ、そうなの?お客様だったの?ごめん!突然きてしまって、どうしようかな。」
佳代は狼狽えた。想定外の出来事だったのだ。そうだよね、お互い離れて暮らしているんだから電話で話すくらいで日常の事なんて分からないんだよね。あぁ~遠距離恋愛は辛い、なんて心の中で独りごとを言っていた。
「どうぞ、中に入ってよ。佳代ちゃんにも紹介するから。」
オサムはドアを開いて佳代を部屋の中に入るようにすすめた。
部屋に入ると見慣れた部屋が、今日は違って見えた。半年の間に少し微妙に変わっていたのだ。リビングの応接セットも模様替えしていたし、飾り箪笥の上も違う。それにお花も飾っている。
ソファーに座ると、オサムの同僚だという女性と目が合った。
「こんにちは。大阪から大変でしたね。疲れたでしょう。」
優しそうな、その女性はオサムよりもずっと年上に見えた。
「いいえ、新幹線は好きですから退屈ではありませんでした。」
佳代は、自分でも何を言っているのか分からないほど頭が真っ白になっていた。いつもなら自分が台所に立ってお茶を入れたり料理を作ったりしていた。
その同じ部屋とは思えないほどの空気感で、自分はここに居てはいけない存在なのだと感じた。
「佳代ちゃん、紹介するよ。この人は、同じ会社の事務をされている人で今日は僕が会社に忘れていた書類を届けてくれたんだ!」
オサムは、佳代の目を少し見てお茶を入れると言って、慌てて台所へ立った。
佳代は自分の浅はかさを恥じた。それでも救われるのは、その女性が優しそうな目をしていた事だ。穏やかなオサムにはお似合いだと思う。
自分はオサムを頼ってばかりだった。遠距離とはいえ、何もしてあげれない。自分の事でいっぱいいっぱいな状態なのだ。仕方がないのかなと思うと嫉妬心も不思議と湧いてこなかったのは何故だろう。
「あっ!オサムさん、お茶は大丈夫です。私、今日は主任の用事で福岡にきたのでちょっと寄っただけなんです。これで失礼します。お邪魔しました。」
佳代は、立ち上がり台所でお茶の準備をしているオサムに声をかけ玄関へ出て、靴を履き始めたらオサムが駆け寄ってきた。
「えぇ!どうして?ゆっくりしていけばいいのに。何も気にしなくていい人だから。」
「ありがとう。でも突然来てしまってごめんなさい。オサムさんにも予定があったのに邪魔してしまったみたいで、また電話しますね。」
佳代はオサムに会いたくて福岡まで来てしまったが、今回は先輩の用事だと心にもない嘘をついた。それだけ言うのが精一杯の佳代だった。
一番辛かったのは、オサムの気持ちが透けて見えたこと。優しいオサムの辛そうな言葉が佳代の頭の中に入り込んでくる。
「ごめんね。佳代ちゃんごめんね。僕は弱い男だよ。寂しかったんだ、ごめんね。」
それから、どう帰ったのかあまり覚えていない。
気が付けば新幹線乗り場の博多駅の構内の人混みの中にいた。どうしよう、大阪に帰らなくちゃいけないんだ。自分の生活はオサムの住む福岡じゃない。大阪なのだからと自分に言い聞かせた。
切符を買い、新大阪行の新幹線を待つホームのベンチに座ると堪えていた涙が一気に溢れてきた。寂しかったと同時にオサムとの思い出が頭の中をぐるぐると駆け巡った。松屋町でオサムと出会った時の事。中之島の図書館での事。
二十歳を過ぎた頃のクリスマスパーティーの事。何度もこの福岡に通って幸せだった時の事。オサムの出張で大阪で時間を惜しんで会った事。楽しかった思い出が次々と現れては消えていくのだった。この腕時計もオサムが買ってくれた、時計を見てもオサムを思い出す。
佳代は、新幹線の列車の中で背中をあずけ目を閉じた。オサムが悪いのではない、仕方がないのだ。人は寂しい生き物、長い間離れていれば、寂しいにきまっている。毎日の生活の中で温もりや触れ合いを探しているのだ。
あの優しそうな女性の目はオサムを幸せにしてくれるだろう。きっとオサムは大丈夫、でも私はどうだろう?私の気持ちは?大丈夫なのか?自分に問う。
大阪の天王寺の佳代のアパートに戻ったのは、夜八時を過ぎていた。部屋に入ると同時、その場に座り込み銭湯へ行く気力も元気も残っていなかった。明日は、早朝から売り出しの準備をしなくてはいけない。気持ちを切り替えなくちゃと自分に言い聞かしていた。